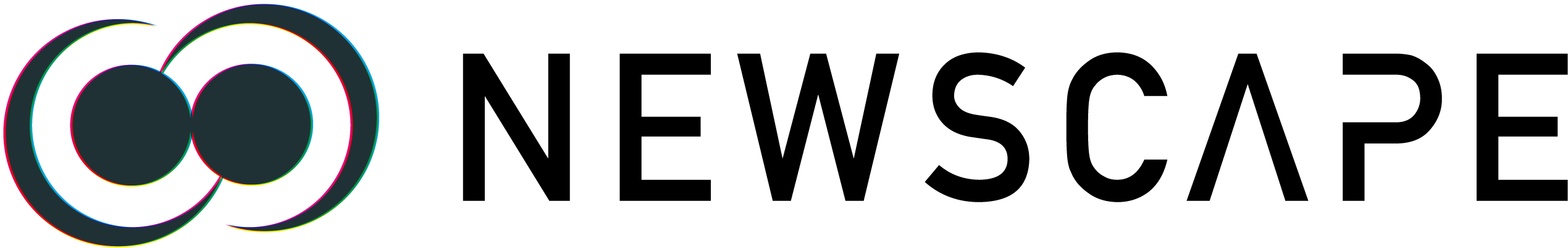Newscape Labの新着記事は、「休暇の人類学――祝祭から権利、そして自己資本投資へ」です。
注目したいのが日本の労働時間の劇的な縮減である。1960年代に年間2,200時間前後で、働きアリとも言われた日本人の平均実労働時間は、バブル崩壊後の約1,900時間を経て、2022年には1,607時間まで低下した。縮減の要因は三つに整理できる。第一に1992年の労基法改正による週40時間制の完全実施。第二に2018年「働き方改革関連法」による時間外労働の上限規制と有給5日取得義務。第三にコロナ禍を契機としたテレワーク普及である。これらが長時間残業文化を揺さぶり、「見せ残業=働いていることを見せる残業」を抑制したと考えられる。
将来の時間縮減シナリオを推計すると、過去60年間で約600時間減った線形ペースと週休三日制の試行拡大を踏まえ、2030年には年間1,500 時間前後(週休2.5日相当)、2050年には1,300 時間台(週休3日に近い水準)まで低下する公算が大きい。製造・医療など時間束縛型職種が残るため1,200時間を切るには追加制度が必要になるが、逆にAIや自動化によって減少がさらに加速する可能性もある。いずれにせよ、余暇へ振り向けられる可処分時間とエネルギーは確実に拡大する。時間的・体力的な余裕が増えれば、休暇はリフレッシュを目的とした「消耗品」ではなく「自己投資の資産」へ変貌する。ポイントは時間を未来へ預けるという発想だ。
(記事は下記リンクからご覧ください)