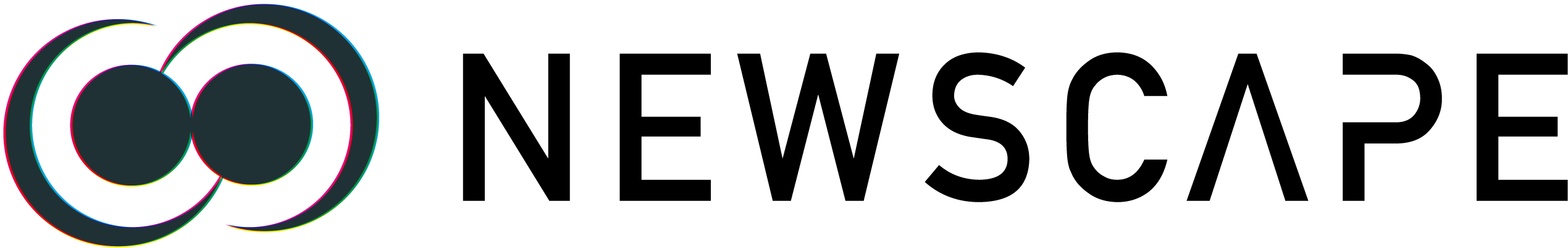本記事は、株式会社ニュースケイプ代表取締役・小西圭介氏によるDIGIDAY寄稿(2021/3/22)記事となります。
スマートフォンに代表される、あらゆる製品やサービスで機能性や日々の生活の合理性が満たされた現代は、便益よりも「不便益」が価値になる時代だ。
世界の音楽市場はストリーミングにすっかり移行した感があるが、2020年は、米国でアナログレコードが前年比46.2%増と、1991年の記録開始以来過去最高の売り上げを記録してCDを追い抜いたという(日本でも2013年以降アナログは再成長市場に転換)。
スマホで撮った写真が翌朝9時まで待たないと現像されないという、時代の利便性に逆行するような写真共有SNS「DISPO(ディスポ)」も最近人気に火がついた。「アナログの復活」という言葉がよく言われるが、アナログ・デジタルを問わず、時間をわざわざ使う“価値ある体験”の再発見・再創造が行われているのだろう。
「文明的」から「文化的」な価値へ
世の中にモノが溢れ、Amazonやコンビニで欲しいものがいつでもどこでも手に入る時代。こうしたなか、進化した機能や効率性よりも自分の好きなこと、大切なことに時間をかけ、意味を感じる体験は、「文明的」価値よりも「文化的」な価値を見出す現代の生活者の価値観を示している。
テクノジーの発展によってもたらされた20世紀の文明的な価値観は、デジタル経済におけるモノと情報の飽和、そして環境問題の深刻化によって、大きな変化を余儀なくされているからだ。
ミレニアルズやGen Zなどの新世代を中心に、モノを所有することに従来のような価値を感じなくなり、特別な体験や消費の社会的影響など、「何を選ぶのか」より、「なぜ選ぶのか」という消費の意味をより重視するようになっている。そして、「商品を買う」のではなく、「価値観に投資する」という消費行動の変化が起こってきている。
「文化的」な価値とは、人に所有の優越性を示すためのブランドの記号でも、空虚な情緒的イメージでもない。意味あることに時間を投資する純粋な喜び、リアルな人の繋がり、経済合理性では解決できない社会問題に取り組むこと、コミュニティに貢献することなどを通じて、人間にとってもっとも価値あるもの、すなわち生きる目的と持続する幸福感を生み出すものだ。
今日のブランドの立脚点も、文明的な価値から人間的・文化的な価値に変化してきている。
いや、売り上げと利益を成長させ、株主価値を高めることを至上の目的としてきた資本主義のビジネスは、社会・文化的価値を正当化するビジネス上の言葉を、「ブランディング」以外にまだ持てていないのではないか(それゆえ、ブランディングは売り上げにつながらない、と批判されることになる。実際はその反対なのだが)。
ビジネスとは、人や社会の課題解決を通じて価値を生み出すものであるが、事業を通じて社会課題の解決を図るCSV(共有価値の創造)(*1)という概念が新たなコンセプトとして語られるのも、モノの需要を満たす今までのビジネスが、いかに狭い市場価値しか見てこなかったかを表していると言えよう。
*1 CSV(Creating Shared Value:共有価値の創造)とは、経営戦略家のマイケル・ポーターが打ち出した概念で、営利企業が社会ニーズ(社会課題の解決)に対応することで経済的価値と社会的価値をともに創造しようとするアプローチ。
こうした流れのなかで、企業が社会的な目的や存在意義を通じて、顧客やステークホルダーの共感や求心力を生み出していく、「パーパス・ブランディング」が近年隆盛になっている。
一方で課題も顕在化している。顧客と同じ価値観を信奉するようなパーパス・ブランディングは、ブランドのユニークな存在意義がない限り、同質化に陥りがちだからだ。 “パーパス・バブル”に埋没して、顧客とのエンゲージメントを築くのが難しくなっているのだ。
これに対して、ダグラス・ホルトは2017年にSNS時代のブランド戦略として、ソーシャルメディア上で生まれる群衆のクラウドカルチャーを活用し、新たに台頭するイデオロギーを支援する「文化的ブランディング」を唱えた(*2)。そこでは、すでに存在している特定のソーシャル・コミュニティの価値観を支援し、影響力を活用しながら、リアルな文化や社会課題に寄り添うムーブメントを増幅することで、消費行動やブランド価値につなげられるというわけだ。
*2 ダグラス・ホルト「クラウドカルチャー:SNS時代のブランド戦略」(ハーバード・ビジネス・レビュー 2017)より
ブランドの文化的な価値への移行は、こうしたコミュニティとの共創が必須だが、決してホルトの言うような流行りのキャンペーン手法でも戦術的なアプローチに止まるものではない。事業を通じた本気の意思とコミットが伴わないと、持続的な価値を創り出せないからだ。そして多くのブランドが、広告やプロモーションから、事業そのものの価値転換に軸足を移し始めている。
たとえば最近マスターカード(MasterCard)は、米国で新たなブランディング・アプローチとして、黒人や有色の女性の起業家・スモールビジネスオーナーを支援し、ベンチャーキャピタルの助成金を提供するコンテストや消費者に紹介するビジネスサポートプログラム・Strivers Initiativeの展開を始めた。
ユニリーバはダブ(Dove)などのブランドで、抑圧された女性のリアルで多様な美の価値観を奨励することで共感を呼んできたが、2021年3月に新たに「ノーマル(普通、標準)」という言葉を広告やパッケージで使用しないことを発表。多様な価値を受け入れ、公平でサステイナブルな美しさを推進して社会変化を促す、ポジティブビューティのビジョンを宣言している。
広告手法ではなくビジネスの当事者として、意思を持って社会を変えるアクションをリードすること。マイノリティの価値観と多様性を支援して新たなビジネスを生み出すこと。文化的価値を重視し持続可能なビジネスに転換すること。賛否両論を超えて、時間をかけて生活者を巻き込みながら、リアルな社会変化の「意味」をもたらすこと。それをブランド・アクティビズムという。
「グローバル化」から「リローカライズ(地場化)」の価値へ
もうひとつこれからのブランドが着目すべきなのは、「リローカライズ(地場化)」の価値である。デジタル化は、文明的な価値提供の標準化をグローバルで一気に進めたが、一方で出自の土地や生産者など、ローカルと結びついた独自価値の重要性を浮かび上がらせた。
地場産業といえば、地方に発祥・歴史を持つ、一次産業や伝統工芸などの産業イメージが強いが、ここで言及しているのは「土地の自然環境や地域文化・コミュニティ固有の潜在価値を発掘し、持続的に価値を高めていく新しい産業のあり方」を意味する。
20世紀型のマスブランドは、効率的な生産と大量供給による規模の拡大という、生産者の都合で生み出されて来たものであり、実は必ずしも消費者ニーズではない。そもそも「消費者」という概念自体もそうだが、マス流通とマス広告によって作られたブランド=「架空の信頼」のシステムによって成長を遂げてきたものだ。
そこでは「同じ品質保証」が大きな価値を担ってきたが、基本的な品質が担保された今の時代には、むしろ自分にとって特別な、ほかにない個性や体験こそが重要になっている。
そして今の考え方は、ブランド=「リアルな繋がりの信頼」なのだ。生活者の価値観は、匿名のモノの消費から、作り手や地域との繋がりにより意味を見出すようになっている。実際のところ、あなたも私もそうではないだろうか?
近年スーパーのビールの棚が、クラフトビールで大きく多様化しつつあるように、地場性を持つことは、マス製品にはない土地固有の物語やリアルな文化体験、人やコミュニティと繋がりという、より価値ある消費の「意味」を生み出すことにつながる。
D2Cブランドの多くがこうした価値に着目しており、近年のマス・カスタマイズや多品種少量生産テクノロジーの成熟とコスト低下も、マス製品の地場化を後押ししている。また、コロナ禍による都市集中の問題などが顕在化するなか、サステナブルな自然環境や地域コミュニティの価値を重視する、社会の価値観シフトが実際に起こり始めている。
セブンイレブンでさえ、画一的な店舗展開と品揃えを見直し、地域別の商品開発や、地域ごとの専用工場を通じてご当地商品を提供する、地産地消のサプライチェーンを強化しはじめている。コロナ禍で生鮮食品を自宅消費する傾向が高まったことで、地場商品の売上が増大しており、同社は日配品の地域限定商品比率を5割まで高めるとしている。
あるいは無印良品は、日本の地域の価値を再編集した商品づくりと社会価値の創造に乗り出している。自治体と組んで設立した複合施設「里のMUJI みんなみの里」では、地域生産者から野菜を仕入れて委託販売やMUJIカフェで提供、また地域農産物の6次化加工を手掛ける「開発工房」もオープンした。
コロナ禍で改めて認識されたのは、人の暮らしの起点はローカルにあるということだ(もちろん東京もローカルである)。土地に根ざしたアイデンティティを持ち、人や地域のコミュニティと繋がり、資源や価値を循環させるサイクルを創り出すこと。これは「ご当地自慢」や「地域ブランド」という言葉で語られた観光消費の世界とは異なる、より持続的な人の繋がりの価値を生み出していく考え方だ。
このことは今後の小売業のあり方にも関わってくる。ECシフトが進み、今やどこにいても同じモノが手に入れられる時代に、フィジカルな店舗の価値は、画一的なチェーンストアや売り場ではなく、ほかにないリアルなコミュニティ体験と、ローカルとの繋がりを生みだす場としての固有性こそが、重要になっていくはずだ。
たとえばナイキが米国をはじめ、コロナ禍で導入した新業態Nike Uniteは、地元の人々がスポーツとより密接につながるのを支援する「ローカルコミュニティの中心的存在」として設計されている。スポーツの持つ本質的な価値である、コミュニティ形成の価値を再定義し、地域の目的地となる新しい場の体験を人々に提供している。
ポストパンデミックの「場」の価値のリデザインは、こうした「リローカライズ」を起点にすべきだ。特に日本は、世界的にも希少な地域の自然・文化・コミュニティの多様性を持ち、地場にこそ日本の未来の強みがあるからだ。
集中から分散化への転換は、今や社会の重要な課題となっている。大企業も含めた新しい「リローカライズ」の価値づくりこそ、循環型経済や社会価値創造の重要なテーマになっていくはずだ。